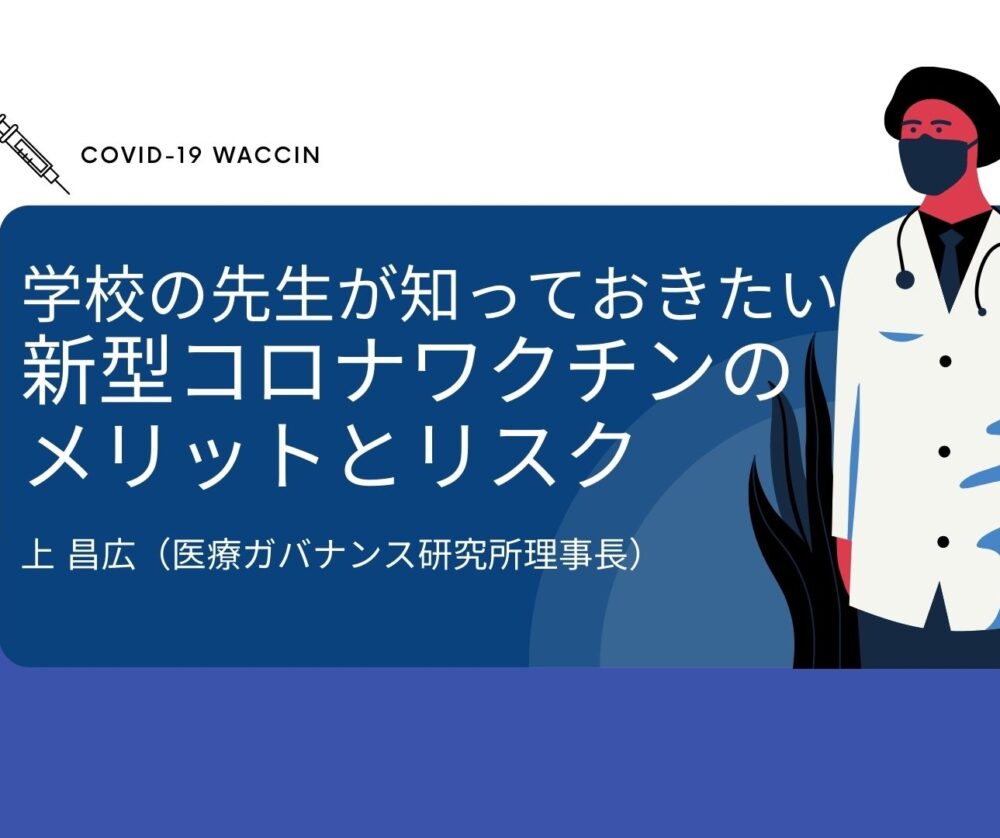目次
新科目「公共」で何を教えるのか
鈴木寛__前半で大野さんから、公共が出口、地理が入口というお話がありましたが、私も同感です。たとえば、公共の重要なテーマの一つに、公共施設の立地についての「NIMBY(ニンビー)問題」というものがあります。”Not In My Back Yard”の頭文字をとってこういうのですが、これはつまり「ごみ処理施設はなるほど必要だ、でもうちの裏庭には作ってくれるな」という話ですね。この問題を考えるときに大切なのは、どこまでが自分の庭で、どこからが他人の庭なのか、まさに地理的な観点です。たとえば日本は福島にいくつも原子力発電所を建て、電力の多くをこれに依存してきました。これが歴史的にいつ始まり、地理的にどのような理由で福島だったのかということをまずは知らなければならない。そして、誰と誰が摩擦を起こし、何と何が板挟みになっているのか、NIMBY問題の所在を明らかにする。これが「歴史総合」「地理総合」の役割だと思います。その上で、これを解決するためにどのような事が考えられるのかを問うのが「公共」の主眼になります。
ですから、たとえば「モンテスキュー、法の精神、三権分立」と教科書に書いてあることを通り一遍に教えていてはダメです。もちろん三権分立は権力が互いにけん制しあうという、とても重要な概念です。しかし、なぜけん制し合うことが必要なのか、権力の当事者たちはどのような関係にあるのか、構造的な理解が伴わないと意味がありません。
総合型選抜と課題解決型学習
鈴木_大学入試の話につなげれば今回「総合型選抜」という、探究活動や特別活動など高校時代の活動を重視した選抜試験が始まりました。これまでは慶応SFCなど一部でしか実施されてきませんでしたが、国立大学でも定員の約3割をこの試験の合格者に充てていくことになりました。すでに2020年度の国立大学の入試でも約2割を越えています。
この試験で問われるのは、PBL(Project Based Learning)です。課題解決型学習と訳されますが、高校生活の中でどのような問題意識をもって学んできたか、そして大学でそれをどのように究めていきたいのかが問われます。課題や問題意識をしっかり持った生徒に大学は来てほしいわけです。そのような文脈で捉えると、社会科はやはり重要な科目であると言えるでしょう。
これからの社会科の先生の役割
大野新__私は長い間、現場の地理教員として中学・高校で教鞭を取ってきました。国立大学の附属校ということもあって比較的自由に授業をやれたこともあり、ディベートをやったり実際に現地に行ったり、課題解決型の授業に力を入れてきたつもりです。その経験から言うと、先生はファシリテイターに徹するということが重要です。よほど議論が危険な方向に行かない限りは極力介入しない、生徒の議論も見守り道筋を作っていくのが先生の役割になります。
先ほどから議論されてきたように「歴史総合」「地理総合」「公共」はいずれも、どのように現実社会を捉えるか、ということに重きが置かれています。したがって教材は現代社会の中にいくらでもあるんですね。ただこれまで行われてきた日本の教育を考えると、どうしても結論を出さなければならない、ある一定の落とし所に持っていかなければならないという意識が先生には強くあると思います。しかし現実社会の課題に向き合えば、そのような模範回答は簡単に出せません。より重要なのは、授業の中でクラスの仲間がどんなことを考えているのか、その考えはどこから生まれたのか、意見が対立したときにどうしたら協調できるのか、そのような生徒の主体的な議論が形成できる空間を作るのが先生の役割になると思います。
確かにこれは教育方法の大転換になるので、これから試行錯誤することになると思いますが、一方で欧米ではすでに当たり前のようにやっていることなんですね。
安心してモノが言える学校とは?
倉石寛__3年ほど前に千葉県にある小さな学校に見学に行ったことがあります。校名に「研究の杜」とある学校で(暁星国際ヨハネ研究の杜コース)、ほんとに教えないんです(笑)小中高一貫校で生徒たちが自分で問いや課題を立てて勉強していくのですが、とにかくよく議論や対話をする。一応授業の時間割はあるんですが、それを過ぎても授業が終わるわけではないと生徒は言うんです。なぜこんなに意欲的なのか?聞いてみたら「安心してモノが言えるんです」という答えが返ってきました。「こんな事言ったら馬鹿にされるんじゃないか」生徒はもちろんですが先生にも「答えられなかったら」といったプレッシャーが普通はあるものですが、ここではそれがない。ではなぜ「自由にモノが言える」環境が出来ているのかというと、ある女子生徒がこんなことを言っていました。「言葉のやりとり以外に、話しぶり、表情、いろんな情報のやりとりがあって、お互いに相手が何を伝えようとしているか、汲み取り理解しようとしている」つまり、うまく言語化できない、上手に議論に参加できない生徒がいても、みんなが助けてくれるんです。そうして自分が考えている以上のことが対話から生まれてくる。これはまさに文字通り「対話的な学び」です。先生と生徒もかなり長く深い対話をする。たとえば進路相談でも1回3時間くらい、6回くらいかけてやるそうです。時間をかけてじっくり対話することで、本人も気付いてなかったことが明らかになるというのはよくあることです。
先生は「教える立場」から「ともに学ぶ立場」へ
倉石_こうした主体的な学びが生まれるもう一つの理由は、先生と生徒の関係です。普通の学校では先生は教える立場で生徒は学ぶ立場で、そこにいわば上下関係がありますが、この学校では「生徒は研究員で、先生は主任研究員」なのです。つまり同じ学ぶ立場に立っているわけです。先生の方がちょっとだけ知識や経験が多いくらいで両者に大きな違いはないということです。先ほどの大野さんの言葉を借りれば先生はファシリテイター、いわばガイド役で授業全体をコ-ディネイトしていく存在なのです。いろんな人が授業に参加するので。
このような考えに立てば、先生もかなりやりやすくなるのではないでしょうか。生徒に質問されて答えられなかったら馬鹿にされるという心配や、あるいは保護者からのクレームに怯えるというようなことはなくなります。生徒と一緒になって考えて答えを出していけばいいんです。
「主体的、対話的で深い学び」は今回の新指導要領の重要なキーワードですが、そんなのは理想論で現実には受験勉強をやらざるを得ない、という先生たちの声はよく聞きます。しかし進路相談でも、偏差値を基準にこの大学、もっと頑張ればあそこの大学というのでなく、生徒が本当に何を学びたいのか対話を通じてじっくり掘り起こしていき、その先に大学入試があるというようにガイドしてあげるのが先生の本来の役割だと思います。
大学入試改革は地域ですすむ
倉石_もうひとつ実例をあげると国立島根大学では「地域志向型入試」という制度を採用しています。これは将来、地元地域のために働きたいという生徒を積極的に入学させる制度で、全学部にあります。面白いのは入試方法で、1回限りのいわゆる面接ではなく大学職員との面談を行っています。面談はたとえば「どんな街を作っていくのか」について職員と対話して考えていくような、ワークショップに近い形になります。この「地域志向型入試」に向けて、大学と高校が連携して街づくりや地域の課題に対する探究活動に参画しているのです。こうした探求型学習とAO入試を結びつけた入試改革は、これからどんどん加速していくと私は思っています。さまざまな形で、いろんな時期に大学入試が行われるようになれば、嫌が上でも高校教育も変わっていかざるを得なくなるでしょう。
社会と高校生をつなぐ社会科
鈴木__なるほど、お二人のおっしゃる通りですね。大学教員の立場から捕捉しますと、学問は問い、問題から始まります。そして問題には3つのフェーズがあります。まず「問題の発見」、次に問題の重要度を見定める「問題の設定」、最後に「問題の解決」となります。これまでは最後の問題解決が重視されてきました。ただしこの複雑で多様化した世界において簡単に解決できる問題はさして重要ではない。もっと言えば解決できない難問の方が多いんです。自戒をこめて言えば我々世代が解決できなかった問題が山積しています。そうなると実は「問題の解決」よりも「問題の発掘」あるいは近い将来大きな問題になるという予測、見極めが重要視されるようになってきています。実際、大学院の研究がそのように変化しています。より重要な問題を認識し、これを次の世代につないで10年単位のスパンをかけて解決に向かおうという流れになっているわけです。次の世代というのはもちろん今の中学生、高校生たちですね。
新型コロナ問題をどう扱うか?
鈴木_しかしいきなり中央政府が抱える難問を高校生に理解させるのは無理があります。だからまずは身近なところから問題意識を持つことが大切です。たとえば新型コロナウイルスについて「命か経済か」という難問があります。これは家庭や学校の中でも起こっています。おばあちゃんのために外出を控えるべきか、お金のためにお父さんは仕事に行くべきかというディレンマですね。あるいは学校も今、子どものために開くべきだがクラスターが起こったらどうするのか、という難問にさらされています。これは今の高校生にとって大変身近でありながら同時に世界が直面している難問でもあるわけです。身近なところから問題を見つけて、似た問題が他でも存在していることを知り、その根源的な理由となっている大きな問題の理解へつなげていく、これはとくに社会科では重要な方法です。
そして問題が難問であれば当然そこには意見の対立、食い違い、矛盾がある。先ほどの学校とコロナのたとえをつなげれば、教育熱心な校長先生は早く学校を開きたい、一方冷静なリアリストである教頭先生は感染予防に万全を期したい、というような対立です。このような食い違いがあるのはある意味当然で、校長と教頭のどちらが正しいとは簡単には言えません。この対立、矛盾をじっくり検討して問題の構造をつかみ解決への糸口を探っていく。まさにヘーゲルの弁証法ですけれど、公共の授業はこれの実践です。いろんな意見をぶつけあい、話し合う中で問題の本質を捉えていく。先生の役割は、ここで議論が簡単に収斂したり、少数の生徒に独占されないように、常に議論にゆさぶりをかけることです。反対意見を引き出し、対話を深めていくファシリテイターの役割が求められます。
社会科の授業と社会参画
大野__私が思うに小・中・高のなかで実は小学校・中学校では、議論して考える授業というのはけっこう行われています。ところが高校になるとぱったりとなくなり、タコつぼ的な知識の詰め込みになってしまっています。私は中高一貫校で教えていたので、中学校でやってきた授業の流れを高校でも引き継ぎたいと思っていました。そこでかつて導入された「総合的な学習の時間」を利用して学習を深めました。しかし、一般的に高校では時間が限られていたこともあり、あまりうまく機能しませんでした。今回の新指導要領はこの対話的学びを限られた時間ではなく、一般教科でも導入しようとするものですから、積極的に取り入れてほしいと思います。
それから中学校と高校の社会科の違いはなにかというと、社会参画という視点の有無ということにあるかと思います。実社会との関連性は高校生になると圧倒的に強くなってきます。具体的な政策提言となると中学生ではなかなか難しいですが、高校生で力量のある生徒であれば可能になってきます。どのように地域社会、地方政治と関わるか、これは社会科のもっとも重要な主権者教育に関わるテーマで、すでに多くの高校、とくに地方では実践しているところも多いと聞きますのでさらに広がっていってほしいと思います。
生徒の「気付き」や「違和感」を大事にする
倉石__そうですね、高校生から大学初めにかけての成長期に自分が直接関わった出来事、そこで感じたことは将来において、とても重要な意味を持つものです。この頃に実感したことは、後の人生の大きな方向を決めるといってもいい。鈴木寛さんも深く関わっておられますがOECDが発表した「教育2030」で強調されているのは「アチチュード」つまり物事に向かう態度です。私なりに言い換えると「感覚」、五感すべてを通じて体験するということですね。高校生が、ある体験をしたときに自分はこう思った、こう感じたという感覚を大切にするということです。たとえば「平等」という概念について知識として持っているだけではダメで、そこに感覚や実感が伴わないと身についたとは言えません。そして高校生は大人にはない、とても鋭敏な感覚を持っているんです。そのような感覚、あるいは「違和感」「気付き」といっていいですが、少し突拍子もない意見だったり、定説からはずれた考えであっても、先生たちは大人の視点からこれを否定したり、受け流すのではなく、広げてあげてほしいと思います。自分で感じたことや考えたことは、その後の人生において決定的な意味をもつこともありますから。
鈴木__OECDの話がでましたけれど、ここでもう一つ強調されているのは「エージェンシー」というワードです。これは「主体性」もっと分かりやすく言えば「当事者性」という意味です。倉石さんのいう「感覚」も当事者として違和感のようなものですね。現実に身の回りで起こっていることに対して、これは違うんじゃないか、もっと違うやり方があるんじゃないか、というような当事者性に基づく違和感です。さらに違和感を持っている当事者というのは社会にいっぱいいるんです。社会から疎外されている人、苦しい立場に置かれている人に取材して、対話をしてその違和感を共有するというのは、社会科の授業の導入としてはとても意味があることだと思います。
他教科とのコラボレーション
鈴木_学校の外に出て関係者を取材するとなると、国語科とのコラボレーションも生まれると思います。取材のお願いの手紙やメールを書く、質問項目を簡潔にまとめる、インタビューの内容を分かりやすく記述する、こうした作業はかなりの国語力を必要としますね。ちょっと余談になりますが、官僚の1年生の仕事は会議の議事録を取ることなんですが、東大法学部を出た人でも最初はまったくこれができません。それで課長あたりにさんざん怒られたりしてるわけです。それくらい取材して話を聞いて内容をまとめるという作業は難しいんです。なので国語の教師の力がぜひとも必要になると思います。とにかく高校はほんとに科目ごとのタコつぼになっていて、横の連携がまったくない。ここもこれから大きく変えていかなければならない。
学校の外に出て取材をする、話を聞くという体験型授業にはいろいろな効果があります。まずクラスや班ごとに取材をすることになりますから協働作業が生まれる。また知らない人に話を聞くというのは、高校生にとっては大きなプレッシャーですから、さまざまなコミュニケーション能力を身につけることが出来る。さらに取材の成果を持ち寄れば、たとえば市役所のお役人が言っていることと、現場の当事者の声に食い違いがあるということもあり得ます。これは先ほど言った「問題の発見」につながり、矛盾をテコにした課題探求学習になっていくはずです。
社会科は実社会に直接つながる教科ですから、そこをベースに他の教科が絡んでくれば、なぜ勉強するのかという動機付けにも役立つと思います。国語はもちろんですが数学だって取材で集めたデータをどう処理するのか、統計学としてコラボすることも出来る。数学の中だけでは社会との接続はなかなか難しいですから。
大野__そうですね、とても重要なご指摘だと思います。私も現役時代に同じようなことは常々感じていました。社会科三科目に加えて、国語、理科、数学が同じテーマで課題探求授業をやるという可能性は今後、十分考えられますね。今は学校ごとに学校設定科目というものを作れますので、この可能性をどんどん広げていってほしいと思います。
それから先ほどお二人から矛盾や問題意識、違和感を大切にするというお話がありましたが私もまったく同感です。全員が大学に進学するわけではないので高校が最後の学びの場になる生徒もいます。今の子供たちは、スマホで検索すればぜんぶ分かると考えてしまっている子がやっぱり多い。しかし、実社会に出ればスマホなんかあまり役に立たなくて、リアルな社会の中で個人として、どう生きていくかが問われます。その時に社会に対する感性やセンサーのようなものが備わっていないと、自分の望む人生を送れないこともあります。社会科はまさに社会に直接向き合う科目ですから、その意味で今後ますます重要になっていくでしょう。
(了)